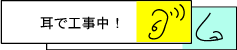 |
 |
| 『聖母たち』 昨年のベルリン映画祭のコンペ作品、ハンスークリスティアン・シュミット監督の『レクイエム』ではにかみやで、敬虔深い田舎の女の子を演じきり、俳優に与えられる銀熊賞を受賞したザンドラ・ヒューラー。もともとは舞台女優(というか今も舞台がメイン)でイェナのシアターハウス、ライプチヒの劇場、そして昨年まではスイス、バーゼルの劇場に居ました。『レクイエム』までは短編映画にちらりと出演しただけ。『レクイエム』でかなり注目度とメジャー度がアップしたのではないでしょうか。1978年生まれの彼女は、30近いとは思えない程に幼い面差しの時も、疲れきって老いて見るときもある不思議な顔だち。髪の毛が短いととてもボーイッシュで男の子みたい。ぼさぼさ髪だと、ほんとにあか抜けない田舎娘な感じ。とにかく、演技がうまい!とつくづく感じさせる女優さんです。 さて、そんなわけで昨年から注目していた彼女の次主演作とあって、見逃せない!とこれまた、風邪ひきを押して見に行きました。 監督は、マリア・スペース(Maria Speth)。もともとは俳優を学んだ後、映画やテレビで編集、監督アシスタントをした後ポツダムのコンラート・ヴォルフ映画学校の『監督』学科に入学。その学校の卒業制作として監督・脚本を担当した映画『In den Tag hinein』が2001年のロッテルダム映画祭で、新人監督に与えられるタイガー・アワードを、クレテイユ国際女性映画祭で審査員賞を受賞。 『聖母たち』 映画は、乳飲み子をかかえたリタ(ザンドラ・ヒューラー)がイライラしながら電話ボックスでいらつきながら電話をしているシーンから始まります。 がちゃんと受話器を投げつける音にかぶるように赤ちゃんの泣き声。 ベルギー。 一軒の家にたどり着いた彼女。『ジェローム・ヴァッセに会いたいの』フランス語をまったく話せない彼女は、そのヴァッセの妻(フランス語しか話せない)と息子(片言の英語を話す)を通じて言葉を交わします。 『あなたはジェロームに何の用なの?』(妻)ー『私の父らしいの』(リタ)盗みなどの罪により、ドイツから逃げ出していたリタを、警官の父、 ジェロームはリタをドイツの警察に強制送還する。 子連れの牢屋(初めて見ました!こういう牢屋もあるんですね)で刑期を勤めた後、出所。 リタはどうやら、ドイツに基地を置く、黒人のアメリカ兵たちと遊び、お金をもらっているよう。 そのお金で3部屋のマンションを借りる。 『ええ、アメリカで離婚してあわてて帰国したもので・・。子どもは3人居ます。』と子どもの出生証明所を出すリタ。 ・・あれ?今居る子どもの他にまだ子どもが? リタの母、イザベラの家には、ファニー、マギー、パウル、イザの4人の子どもたちが居る。どの子も顔だちがばらばらだ。イザベラはレストランを経営していて、いつも夜遅くにならないと帰ってこない。リタの刑期の間、リタは、母イザベラの元に自分の子ども達を預けていたのだった。 リタの元に、付き合いのあったアメリカ兵の一人、マークがソファーベットと巨大なテレビを持ってやってくる。 マークは、彼女の元に居る2歳の男の子、JTをとてもかわいがる。 ・・・そこに、イザベラの家を家出することにしたファニー、マギー、パウル、イザの4人の子どもたちがやってきた。 『こりゃ誰の子なんだ』とマーク。ちなみに、マークは英語しか話せない。 無言の子ども達。『あんたには関係ない』とリタ。 『マイ・ネーム・イズ・マーク。アメリカ兵なんだ』と軍隊式行進を子ども達に教えるマーク。 一番年上のファニーは、リタに 『ねえ、もう子どもを作るのやめられないの』とつぶやく。 マーク、リタ、5人の子ども達。 奇妙な形の家族生活が始まったが・・ |
・・・・私の頭の中に、この映画を見ている間中浮かんでいる映画がありました。それは『誰も知らない』。 『誰も知らない』、良いお父さんが居たバージョン?そんな感じかな?と思ってずっと見ていました。 アメリカ兵のマーク、なんて良いヤツなんだ〜〜!! 『聖母たち』というタイトルだけれど、これじゃ『聖父』。監督インタビューによれば、挑発的な意味で『聖母たち』とつけたよう。 そう、 人は『母』にすぐ母性を求めてしまう。でも、子どもができれば、母性本能があふれるというものではない。どんな女性だって、子どもができれば、それで『母』だ。そこにはなんの聖性も存在しないのだ。 映画の中で、リタの母性“のようなもの”を見せるように思わせながら、監督は観客の甘い希望をすっぱり切り捨てる。 耳に残る、赤ん坊の泣き声が痛々しい。 監督本人も、娘を一人持つ身として、この『女性本能』について疑問が沢山浮かんだそうだ。そして、フランクフルト近くの、子連れ刑務所(?)の取材を始めた。 ザンドラ・ヒューラーの演技はやっぱりすごい。悪女というわけでもなく、ただ、多分人生面倒くさい事は嫌、と思っているだけ、苦しんでいないわけでもなく、でもトラウマがすごくあるわけでもなく。 どこにでもいそうな、と言ってしまうと怖いが、どこにでもいそうな、女の一人。 こんな人を普通に演じられてしまう。 しかし映画は、未消化だったように感じる。 もう少し、リタと母イザベラ、リタと娘ファニー、イザベラとファニーに絞って、母と娘、に焦点をあてて掘り下げて欲しかった。 10点満点として、6くらいでしょうか。 (2007年、ベルリン映画祭観賞記より。批評はその時の気分と私の個人的な好みによるものです。ご了承下さい。) |
 (c)Internationale (c)Internationale Filmfestspiele Berlin |
画像、文章の無断転載を固く禁じます。
All Rights Reserved, Copyright(c)by Hideko Kawachi