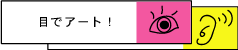 |
||
|
 |
さて、音楽に限らず、キューブリックは完全主義者だったというのは有名な話だが、
私は、この完全主義者と言う事が今回とても気になった。
というのは、ベルリン映画祭で浅野忠信さんが自作短編映画の上映後のインタビューで、
監督としての役割について色々語り、その中で『面白い人を色々知っていて、彼等に、好きなようにやってもらった』と
発言していたからだ。そこで、私は、『監督の役割ってなんだろう?』とちょっと疑問を持ったのだ。 比べるのもなんだが、キューブリックは同じシーンを繰返し繰り替えし、 50回撮影することもざらだったという。 そんなエピソードを聞くと、『コウじゃ無きゃ駄目、コウしてくれないと駄目』と言う監督なのか? と思うが、案外そうでもなかったようだ。 撮影に7年もかけたという“フル・メタル・ジャケット”で主役を演じた俳優は 『どうやって演じれば良いか分りません!』と言ったら『君のままで良い』と言われたそうだ。 無理強いがあるわけではない。魅力が有る人を選びだし、彼等の才能と魅力が集結する。 しかしそれだけではない。監督の頭の中には全ての完成されたビジョンがある。 でもそれをただ再現しただけでは多分、映画にする意味がないのだ。 俳優が、舞台装置が、衣装が、カメラが、音楽が・・様々な人達が監督のビジョンにリンクし、そのビジョンを増幅させていく。 増幅したビジョンをまた監督の厳しい目で選び抜く。 ビジョンがすごければすごい程、多分その増幅の振れ幅も大きくなり、映画もものすごくなるのでは無いだろうか。 今回の展示を見て、何を見ても、キューブリック監督の“ビジョン”が伝わって来るのに驚いた。 左写真の、“シャイニング”の血まみれ廊下のシーンで出て来る、双児の女の子の服。 水色のストライプのパフスリーブ、レースの靴下、黒いエナメル靴。これしかない。 隣にジャック・ニコルソンが使った斧も展示されていたが、普通にぶら下げて展示されているだけなのに、ぞっと来た。 ジャックの笑顔を思い出すからだ・・。あの顔・・あの役はジャックにしか出来ない・・と改めて思う (私はジャック・ニコルソンファン〜!) |
| さて、キューブリックの“ビジョン”がすごい映像を産んでしまった良い例が、“バリ−・リンドン”である。 実は全編通しでは未見なので偉そうに語れないのだが、この映画の中でメインとなる、 ロウソクの光がゆらぐ会食のシーンがある。 ソクーロフ映画の中でもロウソクのシーンがあったが、こちらはフィルターをかけた漆黒の闇の中だった。 しかしキューブリックはロウソクの光だけで、ライトを使わずに18世紀絵画のような、とろりとした陰影を再現。 さて、どうやったのか。 キューブリックはもともとは写真家である。 お父さんが写真好きで、息子を写真家にさせたかったらしい。 そんな父の影響を受けて、子どもの頃から写真に夢中だった彼が16才の時アメリカ大統領ルーズベルトが死去。 アメリカは世界が終わったかのような悲しみに包まれた。 そこで彼は『ルーズベルト死去!』の見出しが踊る新聞を売るスタンドの新聞売りの悲しい顔を撮り下ろし、 その写真は有名雑誌“ルック”に買われ、一躍『天才児現る!』と大騒ぎになった。 カメラマンとして活躍しながら、映画のテーマを見つけ、映画に転向していったわけなのだが、 そんな子ども時代を過ごしたため、カメラについての知識がたっぷりあった彼は、 この“バリ−・リンドン”を撮影するためどんなレンズが必要かが、はっきりイメージされていた。 そのレンズとは、ツァイスがもともとはNASAの衛星写真のために開発したレンズで、 絞りが従来のものより格段に速く、ロウソクの光の中でもキューブリックのイメージするような画を撮る事が可能だったのだ。 ツァイスに頼んでこれを撮影に使用、『18世紀の絵のような』画が完成した。 衣装も、衣装係をオークションハウスに送って、18世紀の衣装のイメージを掴ませた。 『18世紀、しかしカビ臭く無く、生きている、その時代の衣装』という監督の注文にがっちり応えた衣装は 今見ても色褪せず、しかし、歴史物映画によくありがちな妙な今風も感じない。 すごい。 今回、展覧会を見て、彼が写真家だった事を知れたのは面白かった。 現代美術で最近とみに増加しているビデオアート。写真を撮る人の多くがその延長でビデオ・・となる事も多いし、 両手段を使うアーティストも多いが、私にとってはこの2つはとても異なる手段なのだ。 フィルムを撮るということは、時間と空間の流れを考えねばならないという点において、 パフォーマンスに通ずるものがある。むしろ写真は絵画と相通ずるものがある気がする。 話がずれたが、キューブリックの映画は、正に写真からの映像だと思ったのだ。 1シーン1シーンが何かを語る。決まっている。 例えば、ソクーロフの映画をみると、1シーンではなく、全体に流れるたゆたう空間と時間で時間が構成されている感じがするのだ。 鮮烈な色、舞台、衣装、空間。何を見てもばちりと決まっている。 展示を見て、キューブリックの鮮烈な映像美の魅力の背景が伝わって来た。 DVDを買ってしまったのになんだけれど、彼の作品はでもやっぱり色の良い大画面で大音量で、がっちり味わいたい・・。 |
 |
画像、文章の無断転載を固く禁じます。
All Rights Reserved, Copyright(c) by Hideko Kawachi
